中長距離ランナーの筋トレって色々な意見がありますよね。
そもそも筋トレは不要だという声も聞いたりします。
いざ調べてみても、マッチョになりたい人向けの筋トレ方法ばかりが紹介されていたり…
そこで、今回は「中長距離ランナーの筋トレ」について解説しています。
気になったポイントから参考にしてみてください。
中長距離ランナーにも筋トレは必要
結論、筋トレは必要だと言えます。
なぜなら、以下のメリットを得られるからです。
ランニングエコノミーの向上
まず、ランニングエコノミーが向上するというメリットが得られます。
「ランニングエコノミーが向上する」とは「同じ速度をより少ない酸素量で走れるようになる」ということです。

消費する酸素量が少なくなれば、同じペースでも今までよりラクに走れるようになります!
なぜ筋トレによってランニングエコノミーが向上するのか?
それは筋トレによって、地面に力を伝える速度が高まりキック力が上がったり、脚の切替しが素早くなるからです。
筋トレ・補強を行うことでランニングに必要な筋肉が優先的に使われるようになり、その結果、ランニングエコノミーが向上するのです。
「ランニングエコノミーの向上」
- 筋トレによりランニングに必要な筋肉が優先的に使われるようになる
- 地面に力を伝える即速度が高まりキック力が上がる=ストライドの増加
- 脚の切替しが素早くなる=よりピッチを上げられるようになる
ランニングエコノミーは中長距離ランナーの能力を決める重要な要素です。
詳しくはこちらの記事で解説していますので参考にしてください。
神経系の機能発達
また、筋トレには神経系の機能が発達するというメリットがあります。
神経が発達すれば、一度により大きな力を出せるようになります。
なぜなら、全ての筋繊維は神経と繋がっているからです。神経が発達すれば1つの神経で動員できる筋繊維が増え、より大きな力を出せるようになるということです。

1つの神経につながっている筋繊維の数を「運動単位」と言います!
運動単位(1つの神経で動かせる筋繊維の数)を大きくするには、筋肉に負荷をかける必要があります。
また、動員される運動単位は負荷の重さによって変わります。
例えば、手や指を動かすときは小さな運動単位(動かせる筋繊維の数が少ない神経)から動員されます。
一方で、力強い動きをするときは大きな運動単位(動かせる筋繊維の数が多い神経)から動員されます。

このように力を出す時は小さな運動単位から動員されます!これを「サイズの原理」と言います!
運動単位が大きい程、同じペースでもラクに走れるようになります。
そして、運動単位を大きくするには筋トレが必要となるのです。
「神経系の機能発達」
- 筋トレにより運動単位(1つの神経で動かせる筋繊維の数)が大きくなる
- 運動単位が大きくなることで、一度により大きな力を出せるようになる
ケガ・故障の防止
さらに筋トレには、ケガ・故障の防止につながるというメリットもあります。
なぜ筋トレがケガの防止につながるのでしょうか?
簡単な話、ランニングによるケガ・故障は筋力不足が原因であるケースが多いからです。

特に、体幹部の筋力不足によるケガが多いと言われています!
体幹部の筋肉とは、腹筋・背筋・股関節周囲の筋肉のことを指します。
体幹部の筋力が不足していると、膝から下の小筋群に頼る走り方となってしまいます。
この状態が続くと同じ箇所に必要以上の負荷が集中し、その結果ケガにつながってしまうのです。

小筋群に負荷を集中させないためには、体幹部などの大筋群の強化が重要です!
「ケガ・故障の防止」
- 体幹部(腹筋・背筋・股関節周囲)が弱いと、小筋群に頼った走り方になる
- 筋トレを行うと大筋群が優先的に働き、小筋群への負荷の集中を防ぐことができる
中長距離ランナーの筋トレで注意すること
このように筋トレは中長距離ランナーにも多くのメリットをもたらします。
では、中長距離ランナーが筋トレをする際に注意すべきことはあるのでしょうか?
主な注意点としては以下が挙げられます。
筋肥大は起こさない
まず、筋肥大を起こさないということが重要です。
なぜ筋肥大を起こしてはいけないのでしょうか?
それは、いたずらに筋肥大を起こすとパフォーマンスの低下につながってしまうからです。

これにはミトコンドリアや毛細血管の密度が関係しています!
筋肉の細胞内には、ミトコンドリアや毛細血管が存在しています。
毛細血管は酸素を筋肉細胞に届け、ミトコンドリアは届いた酸素を使ってエネルギーを生み出します。
そして、毛細血管やミトコンドリアは有酸素性トレーニングにより数が増えていくのです。

筋肉量に対してミトコンドリアや毛細血管の量が多い程、より効率的にエネルギーを届けられます!
ですが、筋肥大を起こして毛細血管やミトコンドリアの数が変わらなければどうなるでしょうか?
筋肉中の毛細血管やミトコンドリア密度は低下し、酸素の供給率は下がってしまうのです。
つまり、必要以上に筋肥大を起こすと、中長距離ランナーとしての能力は低下するとうことです。
「いたずらに筋肥大を起こさない」
- 筋肉中にはミトコンドリアや毛細血管が存在している
- 筋肉量に対して、ミトコンドリアや毛細血管が多いほどエネルギー供給の効率が上がる
- 筋肉量だけが増えてしまうと酸素の供給率が下がり、中長距離ランナーとしての能力低下につながってしまう
ランニング動作につなげる意識
筋肥大を起こさないことに加えて、ランニング動作につなげる意識を持つことも重要です。
意識なんて精神論じゃないの?と思う方もいるかと思います。ですが、意識をすべき理由がちゃんとあります。

中長距離ランナーの筋トレは、特に意識を持つことが重要となります。
中長距離ランナーの筋トレは、基本的に自重トレーニングから始まることが多いと思います。
字の通り自分の体重が負荷となるので、そこまで負荷は高くありません。
そのため、正確さを求めずに適当に回数を重ねてもトレーニング効果は得られないのです。

例えば、体幹トレーニングを行うときはドローインを意識するとより効果的です!
ドローインとは、へそのあたりを少し引っ込める動作のことを言います。
この状態をキープすることが体幹トレーニングでの基本姿勢となります。
「ランニング動作につなげる意識」
- 自重トレーニング=自分の体重が負荷となるのでそこまで強度は高くない
- それゆえ正確なフォームで行わないとあまり効果は得られない
- ランニング時に使う筋肉を意識することで、よりトレーニング効果が高まる
意識を持つことの重要性についてはこちらの記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
ちなみに、僕自身はランニングに使う筋肉を意識するうえで『最高の走り方』という本を参考にしていました。
基本は「低負荷・高回数」
その他、主な注意点としては「低負荷・高回数」が基本であるということが挙げられます。
先述の通り、中長距離ランナーがむやみに筋肥大を起こすと有酸素能力の低下につながる可能性があります。
そのため、自重トレーニングなどの低負荷・高回数の筋トレを行うことが重要です。

低負荷・高回数の筋トレは筋持久力の向上につながります!
筋肉にかかる負荷の大小によって、動員される筋繊維のタイプは変わります。
例えば、重い器具を挙げれば速筋繊維が動員され、自重トレーニングでは遅筋線維が動員されます。
誤解して欲しくないのですが、遅筋線維だけを鍛えればいいというわけではありません。
1500m3分台・5000m14分台を目指すうえで速筋繊維の強化は欠かせません。
ただし、筋肥大を伴うような筋トレではなく、まずはインターバルやレペティションなどのポイント練習で強化していきましょう。
「基本は低負荷・高回数」
- 遅筋線維が強化され、筋持久力の向上につながる
- 筋肥大を起こすと中長距離ランナーとしての能力低下につながる可能性がある
- そのため速筋繊維はポイント練習(インターバル・レペティションなど)で強化する
中長距離に必要な筋肉
ここまで、筋トレのメリット・注意点について解説してきました。
では、中長距離走に必要な筋肉とは具体的にどの部位を指すのでしょうか?
体幹部
まず、必要となる部位といえば体幹部の筋肉が挙げられます。
「体幹が大切」とはよく聞きますよね。では、なぜ体幹が重要なのでしょうか?
体幹が重要なワケ
体幹が重要な理由には、以下のようなもの挙げられます。
- 上肢から下肢まで関連する運動(ランニングなど)には、体幹の安定が不可欠だから
- 体幹は、骨盤の上に椎体(背骨を構成している小さな骨)が積み重なっているという不安定な構造だから
- 腹腔(骨盤から肋骨の部分)には内臓があり、骨で支える部分が少ないから
※ちなみに椎骨とは↓のことで、椎骨の円柱状の部分を椎体といいます

要するに、「骨で支えられる部分が少ないうえに不安定な構造だから、筋肉を強化して支えよう!」ということです。
だからこそ、体幹トレーニングが重要となります。
体幹部の構成と役割
では、体幹部の構造はどうなっているのでしょうか?
まず、体幹部とは身体の胴体部分のことを指します。
大きく分けると深層の筋肉(インナーマッスル)と表層の筋肉(アウターマッスル)に分類できます。

インナーマッスルとアウターマッスルでは担う役割が異なります!
それぞれの主な役割は以下の通りです。
「インナーマッスル」の役割
- 腹腔をコルセット状に取り囲んで体幹を安定させる
- 横隔膜とともに腹腔の内圧を高めて脊柱を支える
- アウターマッスルの動きに合わせて、骨盤や脊柱を安定させて姿勢が崩れないようにバランスを保つ役割を果たしている
「アウターマッスル」の役割
- 体を前後左右に倒す・ねじるなど、身体を大きく動かす際の主働筋となる
- 重力に抗って直立姿勢を保つ役割も果たしている
※用語について
・腔=体内の中空となっている部分
・腹腔=横隔膜から下の腹壁で囲まれた体内の空間部分
・胸腔=胸郭の内部
・コルセット=胸の下部〜ウエストにかけてのラインを補正するサポーター
・横隔膜=胸腔と腹腔の間にある膜状の筋肉のこと
・脊柱=背骨のこと
・主働筋=身体を動かす時に中心となって働く筋肉のこと
このように体幹部の役割を知ることで、トレーニングへの目的意識を高めることができると思います。

まずは、体幹部の主な役割を押さえるだけでも十分だと思います!
さらに詳しく知りたい方は、以下についても参考にしてください。
まずはザッと見て、「ふーん、こんな役割があるのか…」くらいでいいと思います。
「インナーマッスル」の構成
- 腹横筋=背骨の動きを伝達
- 多裂筋=姿勢を安定させる
- 骨盤底筋群=下から内蔵を支える
- 深部筋群(横突間筋・棘間筋)=背骨の側屈、伸展
「アウターマッスル」の構成
- 腹直筋=体幹の屈曲、背骨の側屈
- 外腹斜筋=体幹の側屈、回旋(反対側)
- 内腹斜筋=体幹の側屈、回旋(同方向)
- 腰方形筋=体幹の側屈(体幹の強い動き)
- 胸最長筋・胸腸肋筋=直立姿勢の維持(体幹運動の主働筋)
筋肉の構成についても詳しく知りたいという方は、図解で覚えることをオススメします。
股関節周り
続いて重要となるのが、股関節周りの筋肉です。
具体的には、大腿部や臀部の筋肉が挙げられます。
股関節周りが重要なワケ
なぜ股関節周りの筋肉が重要なのか?主な理由は以下の通りです。
- 長距離を一定の速度で走りに抜くには、骨盤のブレを抑えることが重要だから
- とくに着地の後、素早く次の動作に移行するためには股関節周りの筋肉が重要となるから
先述のとおり、膝から下の小筋群に頼ってしまうとケガにつながります。
そのため、とくに着地の際などは大腿部や臀部を優先的に使える身体にしておくことが大切です。
股関節周りの構成と役割
大腿部と臀部それぞれの構成については以下の通りです。
「大腿部」の構成
- 大腿筋膜張筋・腸脛靭帯=股関節の外転、屈曲、内旋、膝関節の伸展
- 腸腰筋(大腰筋・腸骨筋)=股関節の屈曲、骨盤の前傾
- 股関節内転筋群=股関節の内転
- 長内転筋
- 薄筋
- 縫工筋=股関節の屈曲、外転、外旋、膝関節の屈曲、内旋
- 大腿四頭筋=膝関節の伸展、股関節の屈曲
- 大腿直筋
- 中間広筋
- 外側広筋
- 内側広筋
- 大内転筋=股関節の内転、外旋
- ハムストリングス=股関節の伸展、膝関節の屈曲および内旋
- 大腿二頭筋
- 半腱様筋
- 半膜様筋
「臀部」の構成
- 中臀筋=股関節の外転
- 大臀筋=股関節の伸展
※用語について
・外転=腕や脚を身体の正中線から遠ざける動きのこと(垂らした腕を真横に上げるなど)
・内転= 〃 身体の正中線に近づける動きのこと(開いた脚を閉じるなど)
・外旋= 〃 位置は変えずに体の外側に向かって回転させる動きのこと
・内転= 〃 位置は変えずに体の内側に向かって回転させる動きのこと
・正中線=人・動物の中央を縦にまっすぐ通る線のこと
オススメの筋トレ・補強メニュー
今回ご紹介するメニューは一例です。
人によってウィークポイントは異なるので、まずは様々なメニューを試して自分に必要なメニューを見つけていきましょう。
ステップアップ・背筋・ランジ
「ステップアップ」:左右 各10回×3セット
- 台の上に片足を乗せる
- 膝・股関節を伸ばして体を引き上げて、台の上に片足で乗る
- 台から足を下ろして元に戻る
- 足を変えて上がる
「背筋」:30回
- 腹ばいになる
- 両手両足を挙げ、背中を反らす
- 胸と両膝をしっかり床から離す
「ランジ」:左右 各15回×3セット
- 足を肩幅くらいに開いて姿勢良く立つ
- 大きく1歩前に踏み出す(股関節を地面につけるイメージ)
- 足を下げて元の位置に戻る
体幹トレーニング
体幹トレーニングについては、なかやまきんに君さんのこちらの動画がオススメです。
「どれから始めればいいのか分からない」という方は、こちらのメニューを3〜6セットやってみてください。
ちなみに、なかやまきんに君さんの動画はメニューのポイントが詳しく解説されているので、意識性の原則という点でも非常にオススメです。
ジャンプ系トレーニング
ジャンプ系トレーニングは接地の衝撃が大きいため、ケガを防止するために十分に体幹を強化しておく必要があります。
「バウンディング」:左右 各5回×3セット
- 素早く力強く蹴る
- 大きく腕をスイングさせて推進力を得る
- 上り傾斜を利用すると良い
「ヒルランニング」:左右 各10回×3セット
- 上り傾斜を利用して腿上げ
- 進む距離は20〜40cm程度
- 上半身が倒れないように姿勢はまっすぐに保つ
「ダブルホップ」:3〜5回×3セット ※柔らかい地面で行う
- ジャンプして素早く両足を抱え込む
- 着地と同時にまたジャンプする
- マーカーなどを80〜90cm間隔でセットして実施
モチベーションが上がらないときは
なかなか効果を実感できなくて、モチベーションを保てないときもあると思います。
そんな方はこちらの記事を参考にしてみてください。
どれくらいで効果が出るのか、ある程度の目安が分かればモチベーションも維持しやすくなります。
まとめ
結論、中長距離ランナーにも筋トレは重要です。
そこで今回は、筋トレのメリット・注意点・必要な筋肉について解説してきました。
- ランニングエコノミーが向上する
- 神経系の機能が発達する
- 故障・ケガの防止につながる
- いたずらに筋肥大を起こさない
- ランニング動作につなげる意識を持つ
- 基本は「低負荷・高回数」
- 体幹部
- 股関節周り(大腿部・臀部)
筋トレは自宅で今すぐにでも始められます。簡単なメニューからさっそく実践してみましょう。
ただ、いざ筋トレを始めてみようと思ったものの…「筋トレとランニングのどちらを先にやるべきか」が分からないこともあるかと思います。
そんな疑問について、こちらの記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
『基礎からわかる!中長距離走トレーニング』(櫛部静二 著)
運動生理学やスポーツ科学に基づいた内容となっていて、すぐにでも応用できる知識がたくさん記されています。
非常に面白く、モチベーションアップにも繋がります。
- 著者は城西大学駅伝部監督の櫛部静二さん(櫛部監督は3000mSCの前日本高校記録保持者)
- 実際に箱根駅伝に出走した選手の「レース直前の調整メニュー」が記載されている

陸上ブログの”Y-RUNNING.COM”を運営している” Y”といいます。詳しいプロフィールはこちら。この記事が気に入ったら、Twitterなどでシェアしてもらえると嬉しいです!

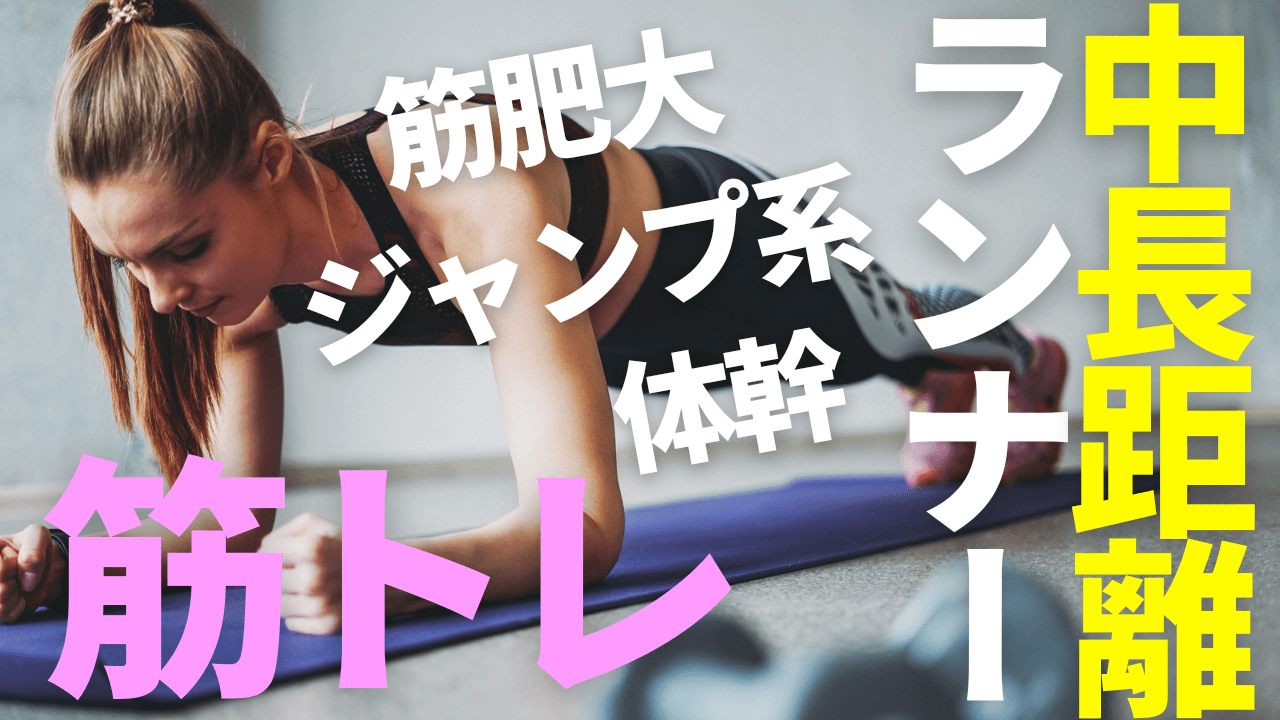
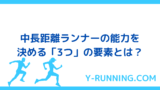
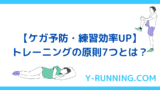
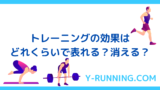
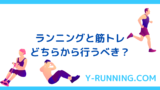
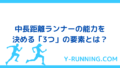
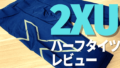
コメント